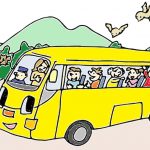少子高齢化の進展に伴い、特に中小企業においては今後後継者不足の問題もあり廃業や事業継承などの取り組みが活発化されることが予想されています。
実際に黒字経営にも関わらず、休廃業や解散した企業は6割にも上るという統計データもあるのです。
このような背景からM&Aや事業売却を行う会社も増えてきており、国でも中小企業庁が手続きの在り方などの検討を始めました。
将来的には許認可制にもなる可能性もあり、市場としても非常に大きなものになっています。
https://syunik.org/venturesupportuser.html
https://syunik.org/futuregrowth.html
光本勇介氏が考える株式会社の売却
会社や事業を売却するということには、いろいろな方法があります。
まず株式会社自体を売却する場合は、その会社の価値を算定して株式を買い取ることでその会社を支配下にすることで成立します。
この場合社内における資産や現金などの価値とともに、従業員も含めた資産価値を算定するのが一般的です。
算定方法にも様々なものがあって、現状の価値や将来的な成長も含めた価値算定を行う場合もあります。
そして売る側と買う側で双方が合意する必要がありますが、売る側からすれば出来るだけ高く買いたいですし買う側から見ればリーズナブルに購入したいというのが通常です。
このため間に入る仲介業者が重要な役割を担うのですが、その場合に手数料をもらうことでビジネスが成り立ちます。
M&Aの場合は、会社そのものを買い取るため株主が変わるだけで従業員などの処遇については買収時は大きくは変わりません。
一方で役員の場合は、株主が選出するものであることと会社の支配下に置くのが普通なので経営層は変わることがあります。
もちろん、いきなり社長交代というと社内に動揺が広がるため社長はそのまま据え置きますが過半数を買収した役員で占めるのです。
参照/光本勇介
事業譲渡の場合
一方の事業譲渡の場合は、事業だけを切り出して別の会社に移設するような内容のため従業員側の処遇が変わることになります。
この場合、従業員は売る側の会社から買う側の会社へ移籍するこのになります。
移籍にあたっては雇用契約主が変わるため、手続きを行うための書面での同意を設ける必要があるのが一般的です。
このため従業員が条件面で納得いかない場合は、譲渡前の会社に残るか会社を去るかの選択を迫られることになるのです。
また従業員が別の会社の従業員になった後も、会社の仕組み自体が大きく変わることになります。
具体的には日々の勤怠の付け方だったり経費の処理方法などは、売渡先の会社のシステムを利用することになるため最初は不慣れな部分も出てくるでしょう。
高額な買い物であることと、様々なリスクがあることから手続きにあたっての価格算定には金額面だけでなく、法的な側面からも調査が入ります。
例えば反社会的勢力が売る側の会社に含まれていると、それだけで様々なリスクが発生します。
まず銀行からの取引ができなくなってしまうため、最初に調べるものといってよいでしょう。
ビジネスモデルについても確認対象
このほかビジネスモデルについても違法性が無いかや、各種法令違反がないかなども確認対象です。
仮に法令違反がある場合は、軽微なものだと買収後に直すことも可能ですが重大なものの場合は購入前に改善する必要がある内容のものもあります。
一方の会計面では、様々な会社におけるリソースを全て評価し算定したうえで価格を決めていく重要なものです。
もし買収する会社にメーカーや設備投資がある場合は、これらの物品も価格算定を行う必要があります。
具体的にあ貸借対照表を確認し、必要に応じて実地調査や伝票などの帳票の収集も行い価値を算定ししていきます。
事業売却の場合だと設備投資も含めて購入するかどうかで価格も異なってきますし、事業自体の利益も重要な要素になります。
これらをすべて算定しておおよその相場も含めて、購入価格の範囲を決めていきます。
価格が決まったら売り手と買い手が価格について交渉を行い、各機関で決済を行えば契約上の手続きは完了です。
雇用の確保など背景の説明の仕方によってはトラブルになりかねない
次に従業員への説明を行っていくのですが、この場合雇用の確保など背景の説明の仕方によってはトラブルになりかねません。
入念な準備を行った上で、丁寧に説明する必要があるでしょう。
基本的に処遇が現状のままだったり良くなったりする場合は、ほとんど問題は生じません。
一方で処遇が悪くなる場合は、慎重な対応が求められます。
特に従業員は労働基準法によって手厚く保護されていることから、できるだけ処遇はそのままに出来るような方法を検討することが賢明です。
どうしても変える必要がある場合は不利益変更としての説明に加えて、従業員への同意書をとる必要が出てきます。
もし同意を拒否された場合、会社側に移籍の権利はなく元の会社に残る必要が出てきます。
まとめ
この場合も残る会社の従業員の配置て難など、別の課題も出てきますので注意が必要です。
いずれにしても、さまざまな課題をクリアしてようやくM&Aや事業売却が成り立つということは覚えておく必要があるといって良いでしょう。
最終更新日 2025年5月12日 by syunik