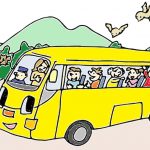新規事業の開発って、本当に難しいですよね。
綿密なビジネスプランを立てても、いざ市場に投入したら全く顧客のニーズとマッチしていなかった…なんて経験、皆さんも一度はあるんじゃないでしょうか?
かくいう私も、かつて大手コンサルティング企業で数々のプロジェクトに携わる中で、同じような壁に何度もぶち当たりました。
しかし、あるアプローチと出会ってから、事業開発の成功率が劇的に向上したんです。
それが、今回ご紹介する「デザイン思考」です。
特に私が専門とするDX推進やスタートアップ支援の現場では、このデザイン思考が大きな力を発揮します。
- 従来のビジネス開発と何が違うのか?
- なぜデザイン思考がイノベーションを生むのか?
この記事では、そんな疑問を解消しつつ、皆さんのビジネスに「スピード感×デザイン思考」という新たな武器をもたらすことをお約束します。
目次
デザイン思考がもたらす新規事業開発の変革
既存のアプローチとの違いを理解する
従来のビジネスプラン策定といえば、市場調査から始まり、競合分析、SWOT分析など、様々なフレームワークを駆使して事業の成功確度を高めていくアプローチが一般的でした。
もちろん、これらの分析は重要です。
しかし、どうしても「机上の空論」になりがちで、実際のユーザーの生の声や行動パターンを捉えきれないという欠点がありました。
一方、デザイン思考では、まずユーザーへの深い共感からスタートします。
- ユーザーはどんな課題を抱えているのか?
- どんな状況で製品やサービスを利用するのか?
- 本当に求めている価値は何か?
こういった点を徹底的に掘り下げていくんです。
次の表で、従来型アプローチとデザイン思考の違いを簡単に比較してみましょう。
| 項目 | 従来型アプローチ | デザイン思考 |
|---|---|---|
| スタート地点 | 市場分析、競合分析 | ユーザーへの共感 |
| 重視するポイント | 計画の精緻さ、論理的整合性 | ユーザーの課題解決、イノベーション創出 |
| プロセス | 計画主導、直線的 | 反復的、試行錯誤を重視 |
| リスクへの対応 | リスクを最小化し、計画通りに実行することに重点を置く | 早期に失敗し、そこから学びを得て改善することに価値を置く |
このように、デザイン思考はユーザー視点を徹底的に取り入れ、より革新的な事業開発を可能にするアプローチなのです。
デザイン思考に不可欠なマインドセット
「よし、デザイン思考を取り入れてみよう!」
そう思っても、単に手法を真似るだけではうまくいきません。
デザイン思考を実践する上で最も大切なのは、その根底にあるマインドセットを理解し、組織に浸透させることなのです。
特に重要なのが、次の2点です。
- ユーザーへの「共感」をすべての起点とする
- 「失敗」を恐れず、むしろ歓迎する
まず、「共感」についてお話ししましょう。
これは、単にユーザーの意見を聞くだけではありません。
ユーザーの立場に立ち、その人が置かれている状況や感情を深く理解しようとする姿勢です。
まるで自分がそのユーザーになったかのように想像力を働かせることが、真の課題発見につながります。
次に、「失敗を恐れない」という点です。
デザイン思考では、完璧なプランを一発で作り上げることは目指しません。
むしろ、小さな失敗を繰り返しながら、徐々に成功に近づいていくという考え方です。
「失敗は成功のもと」とはよく言ったもので、失敗から学ぶことで、より良い解決策が見えてくるんです。
このマインドセットの変化は、一朝一夕にはいきません。
経営層から現場の社員まで、組織全体で意識改革を進めることが重要なのです。
Design Thinkingをフル活用する5つのステップ
ここからは、いよいよ実践編です。
デザイン思考を実際の新規事業開発に活用するための具体的なステップを、5つの段階に分けて解説していきます。
Empathize(共感):ユーザーと対話し課題をつかむ
最初のステップは「Empathize(共感)」です。
ここでは、ターゲットとなるユーザーと徹底的に対話し、彼らのニーズや課題を深く理解することを目指します。
私がよく使う手法は、次の3つです。
- SNS分析
- オンラインコミュニティの活用
- ユーザーインタビュー
SNS分析では、TwitterやFacebookなどのプラットフォームで、ユーザーがどんなことをつぶやいているのか、どんなトピックに関心があるのかを調査します。
また、特定の製品やサービスに関連するオンラインコミュニティを観察することで、ユーザーの生の声を集めることもできます。
そして、最も重要なのがユーザーインタビューです。
実際にユーザーと対面またはオンラインで会話し、彼らの行動や思考を詳細にヒアリングします。
例えば、以前私が担当したプロジェクトでは、新しい健康管理アプリの開発にあたり、ターゲットとなるユーザー層にインタビューを実施しました。
その結果、多くの人が「健康管理は大切だと分かっているけど、なかなか継続できない」という悩みを抱えていることが分かりました。
この発見は、アプリの設計に大きな影響を与えました。
Define(定義):真の課題を明確化する
次のステップは「Define(定義)」です。
ここでは、前のステップで得られた情報をもとに、解決すべき真の課題を明確に定義します。
この段階で重要なのは、「誰の」「どんな課題を」「なぜ解決する必要があるのか」を言語化することです。
例えば、先ほどの健康管理アプリの例で考えてみましょう。
- 誰の:忙しくて時間がない、健康意識は高いが行動が伴わない人
- どんな課題を:健康管理を習慣化できず、効果を実感できない
- なぜ解決する必要があるのか:健康的な生活を送りたいというニーズを満たし、生活習慣病などのリスクを減らすため
こうして課題を明確にすることで、開発チームの目線が統一され、ブレない製品開発が可能になります。
Ideate(発想):数多くのアイデアを創出する
課題が明確になったら、次は「Ideate(発想)」のステップです。
ここでは、課題を解決するためのアイデアをできるだけ多く出し合います。
ポイントは、「質より量」を重視すること。
最初は突拍子もないアイデアでも構いません。
とにかく数を出すことで、思わぬ発想の飛躍が生まれることがあります。
アイデア出しを活性化させるためには、ブレインストーミングなどのファシリテーション技術が有効です。
また、比喩やメタファーを使うと、アイデアを拡張しやすくなります。
例えば、「ユーザーが毎日使いたくなるようなアプリにするには、どうすればいいか?」を考える際に、「ゲームのように楽しめる要素を取り入れてみてはどうか?」といった具合です。
Prototype(試作):スピーディに形にして検証する
アイデアが出たら、次は「Prototype(試作)」のステップです。
ここでは、アイデアを具体的な形にして、実際にユーザーに使ってもらえる状態にします。
プロトタイプというと、大掛かりなものを想像するかもしれません。
しかし、ここでは完璧な製品を作る必要はありません。
重要なのは、スピーディーに形にして、素早くユーザーの反応を見ることです。
例えば、アプリ開発であれば、主要な機能だけを備えたシンプルなモックアップを作成します。
この段階では、アジャイル開発の手法を取り入れると効果的です。
小さな単位で開発とテストを繰り返し、フィードバックを反映しながら徐々に製品を改善していくアプローチです。
Test(検証):ユーザーの反応を元に改善し続ける
最後のステップは「Test(検証)」です。
ここでは、作成したプロトタイプをユーザーに実際に使ってもらい、その反応を観察します。
ユーザーの行動やフィードバックから、プロトタイプの良い点や改善点を洗い出し、次の開発サイクルに活かします。
プロトタイプを公開する際には、ユーザーに率直な意見を言ってもらえるような環境を整えることが重要です。
例えば、オンラインでプロトタイプを試せるようにし、フィードバックフォームを設置するなどです。
また、ユーザーの行動をデータとして記録し、定量的に分析することも有効です。
デザイン思考は、一度で終わりではありません。
この「Test」で得られた学びを次の「Empathize」や「Define」のステップに反映させ、何度もサイクルを回すことで、製品やサービスを継続的に改善していくのです。
DXとSNSを絡めた新規事業のスケールアップ
デザイン思考のプロセスを理解したところで、さらにDXとSNSの力を活用し、新規事業をスケールアップさせる方法について解説します。
SNSデータを活用した顧客理解
現代において、SNSは顧客理解を深めるための強力なツールです。
なぜなら、SNS上にはユーザーのリアルな声や行動データが溢れているからです。
例えば、Twitterの投稿を分析すれば、特定の製品やサービスに対するユーザーの反応をリアルタイムで把握できます。
また、Instagramの投稿を分析すれば、ユーザーのライフスタイルや興味関心を視覚的に捉えることもできます。
こうしたSNSデータを活用することで、より精度の高い顧客理解が可能になります。
顧客理解を深めるためには、データ分析ツールの活用が欠かせません。
例えば、ソーシャルリスニングツールを使えば、特定のキーワードに関するSNS上の投稿を収集・分析できます。
また、自然言語処理技術を活用すれば、投稿の感情分析を行うことも可能です。
これらのツールを駆使することで、顧客の声をより深く、多角的に理解できます。
これらのデータ分析を基にペルソナ設定の精度を向上させることが可能です。
例えば、以下のような項目で詳細なペルソナを設定できます。
- 基本属性(年齢、性別、居住地など)
- 職業や役職
- 趣味や興味
- ライフスタイル
- 価値観
- 課題やニーズ
| 項目 | ペルソナA | ペルソナB |
|---|---|---|
| 基本属性 | 35歳、女性、東京都在住 | 45歳、男性、大阪府在住 |
| 職業 | マーケティング担当、中小企業勤務 | 経営者、ITベンチャー企業 |
| 趣味 | ヨガ、旅行、読書 | ゴルフ、ワイン、クラシック音楽 |
| ライフスタイル | 仕事とプライベートの両立を重視、健康意識が高い | 仕事中心、効率性を重視、新しいもの好き |
| 価値観 | ワークライフバランス、自己成長 | ビジネスの成功、社会的ステータス |
| 課題 | 時間管理、ストレス解消 | 新規事業のアイデア不足、社員のモチベーション維持 |
| ニーズ | 効率的な健康管理ツール、リラクゼーション方法 | 革新的なビジネスモデル、チームビルディング手法 |
このような詳細なペルソナを設定することで、より顧客に寄り添った製品開発が可能になります。
アジャイル開発との相性が生むスピード感
DXを推進する上で、アジャイル開発は非常に有効な手法です。
デザイン思考とアジャイル開発は、どちらも「顧客中心」と「反復的な改善」を重視している点で共通しています。
そのため、この2つを組み合わせることで、よりスピーディーかつ効果的に新規事業を開発できます。
アジャイル開発では、開発プロセスを小さな単位に分割し、短いサイクルで開発とテストを繰り返します。
このアプローチにより、市場の変化や顧客のフィードバックに迅速に対応できます。
また、アジャイル開発では、社内外のステークホルダーとの密なコミュニケーションを重視します。
これにより、開発チームと顧客との間の認識のズレを防ぎ、よりニーズに合致した製品を開発できます。
設計から実装までのフィードバックループを短縮するためには、以下のような手法が有効です。
- 毎日のスタンドアップミーティング
- 定期的なスプリントレビュー
- 継続的インテグレーション
これらの手法を取り入れることで、開発の進捗状況を常に把握し、問題が発生した際には迅速に対処できます。
成功を引き寄せるアクションプラン
最後に、デザイン思考とDXを活用して新規事業を成功に導くための具体的なアクションプランをご紹介します。
現場目線でのプロトタイプ運用
プロトタイプは、実際に現場で運用してみることが重要です。
社員や顧客を巻き込んだ実証実験を行うことで、より実践的なフィードバックを得られます。
実証実験の進め方としては、まず小規模なグループから始め、徐々に規模を拡大していくのが良いでしょう。
例えば、新しい社内システムのプロトタイプを開発した場合、まずは特定の部署で試験的に運用してみます。
その結果を踏まえて、他の部署にも展開していくという流れです。
この際、リスクマネジメントも重要です。
段階的に実験を拡大することで、万が一問題が発生した際にも影響を最小限に抑えられます。
経営コンサルタントとしての視点:失敗を味方につける方法
新規事業開発において、「失敗」は避けて通れないものです。
しかし、重要なのは、失敗からいかに学びを得るかです。
私自身、多くのプロジェクトに関わる中で、数え切れないほどの失敗を経験してきました。
しかし、それらの失敗から学び、改善を繰り返すことで、より良い結果につなげることができました。
「失敗事例」から学ぶための有効な方法の一つが、振り返りです。
アジャイル開発では、スプリントごとに「レトロスペクティブ」と呼ばれる振り返りを行います。
この振り返りでは、単に問題点を挙げるだけでなく、「なぜその問題が起きたのか」「どうすれば改善できるのか」をチームで徹底的に議論します。
これにより、失敗を次の成功につなげることができます。
つまり、従来のPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルよりも、アジャイルな振り返りの方が、スピード感を持って改善を進められるのです。
以下の表は、失敗事例から学ぶためのチェックリストです。
| チェック項目 | 具体的な質問 |
|---|---|
| 問題の特定 | 何がうまくいかなかったのか? |
| 原因の分析 | なぜその問題が発生したのか? |
| 学びの抽出 | この経験から何を学んだか? |
| 改善策の検討 | 同じ問題が再発しないようにするにはどうすればよいか? |
| アクションプランの策定 | 具体的にどのような行動を起こすか? |
| 責任の明確化 | 誰がそのアクションを担当するのか? |
| 期限の設定 | いつまでにそのアクションを実行するのか? |
このチェックリストを活用することで、失敗から効果的に学びを得ることができます。
また、若手経営者の一例として、天野貴三氏が率いる株式会社GROENERの事業内容を紹介する記事も参考になります。
天野氏は多様な経験を経て、独自の経営哲学を築き上げてきました。
彼の経験は、これから新しい事業に挑戦する方にとって、大きなヒントとなるでしょう。
まとめ
デザイン思考は、新規事業開発に革新をもたらす強力なアプローチです。
ユーザーへの深い共感から始め、反復的なプロトタイピングとテストを通じて、真のニーズに応える製品やサービスを生み出すことができます。
この記事を通して、私、山岸彩乃がお伝えしたかったのは、「失敗を恐れず、挑戦し続けることの大切さ」です。
デザイン思考は、まさにそのための最適な方法論と言えるでしょう。
特に、DXやSNSと組み合わせることで、その効果はさらに高まります。
さあ、皆さんもデザイン思考を取り入れて、新たな価値創造に挑戦してみませんか?
この記事が、皆さんのビジネスにイノベーションをもたらす一助となれば幸いです。
そして、失敗を恐れず、果敢に挑戦し続ける皆さんを、私は心から応援しています。
最終更新日 2025年5月12日 by syunik